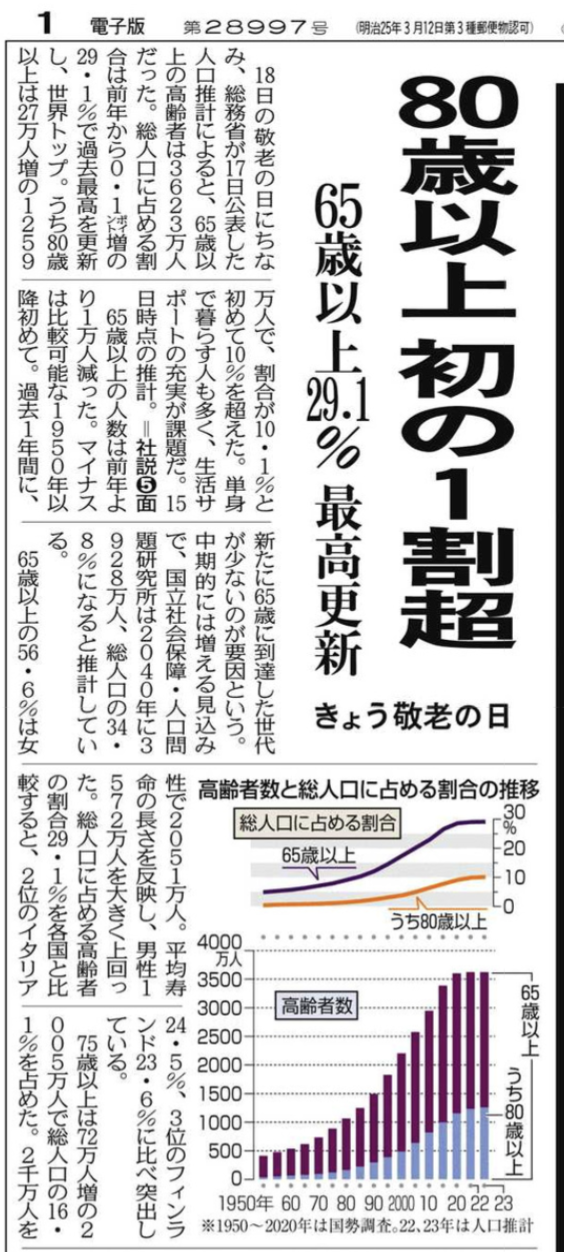本日の東京新聞夕刊に、イランの女性人権活動家のモハンマディさんがノーベル平和賞を受賞した記事が掲載されていた。イラン政府がイスラム教の教義を利用して人権侵害や表現の自由を奪っているというノーベル賞委員会の見解と、ノーベル平和賞の政治利用であり、欧米によるイスラム教への冒涜だとするイラン政府の批判が渦巻く受賞となっているようだ。
「希望の竿燈」
本日の東京新聞夕刊に、東北三大祭りの一つである秋田の竿燈が取り上げられていた。
1学期に取り上げた私大の入試問題に祭りに関する問題が出題されたので、簡単に復習しておきたい。
以上が「東北三大祭り」だが、東北6県の他の3県から指摘があったのだろうか。岩手、山形、福島の祭りも加えて紹介している観光サイトが多い。ただし、最後に取り上げる福島は、県全体を代表する祭りではなく、福島市だけの祭りであり、いわき市や会津若松市、郡山市では独自の祭りが行われている。このあたりは幕末の抗争を経て福島県が誕生した歴史に照らし合わせると面白いかもしれない。
「インド、南シナ海関与強化」
本日の東京新聞朝刊に、インドがフィリピンやベトナムとの軍事連携を強化し、南シナ海でのプレゼンスを高めていくという記事が掲載されていた。全くもって意味のない不要な緊張を招くだけの外交である。貧困や洪水で困っている人たちのためにこそ財政を動かしていくべきである。アメリカに追随するだけでよいのだろうか。非同盟・全方位外交の伝統はどこへ行った?
歴史に踏み込むと、かつてインドは日本の独立(米国隷属)を果たしたサンフランシスコ平和会議に参加しなかった国の一つである。インド・ビルマ(ミャンマー)・ユーゴスラヴィアの3カ国は、講和後における外国軍隊の駐兵を予見するような平和条約の規定や賠償問題への不満などを理由に会議への不参加を表明している。
様々な軋轢を抱える南アジアの盟主であるインドには、1955年のアジア・アフリカ会議でネルー首相が提唱したように、アメリカにもロシアにも属さない第3世界の結集軸として存在感を示してほしい。