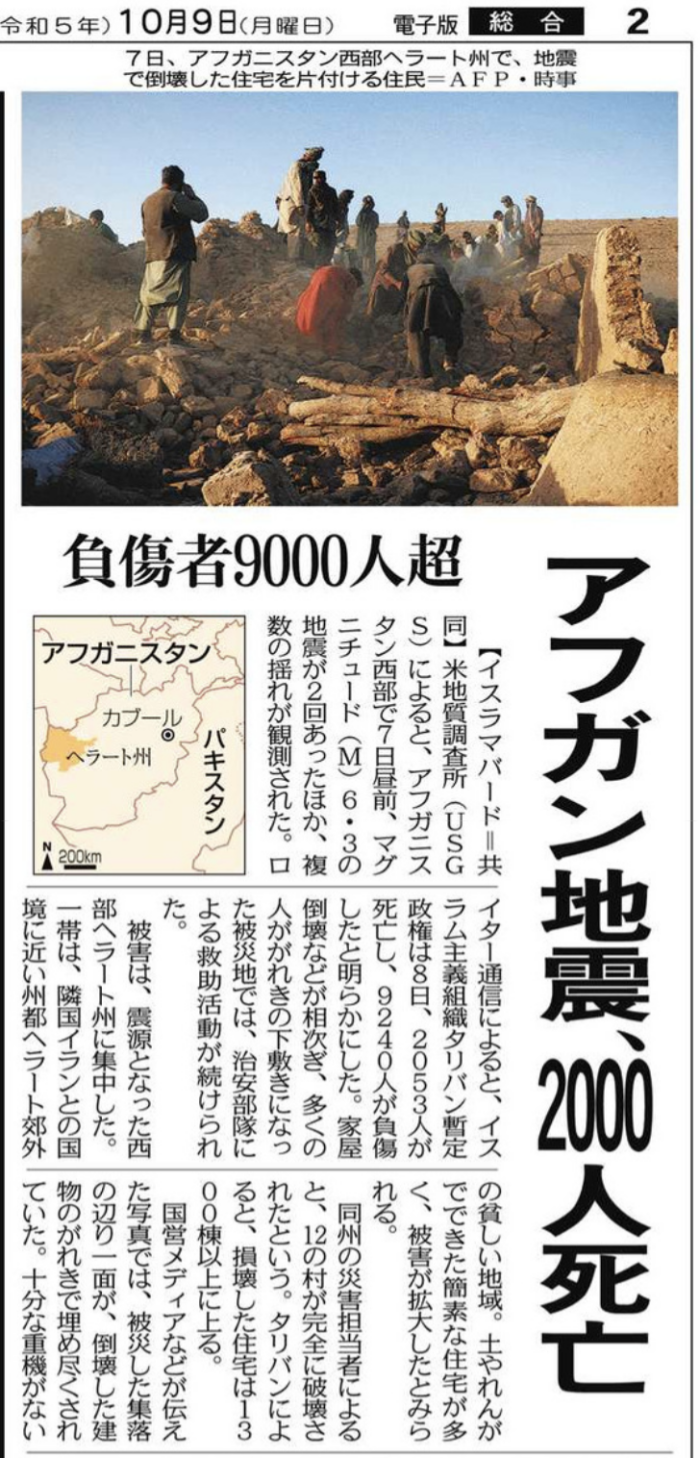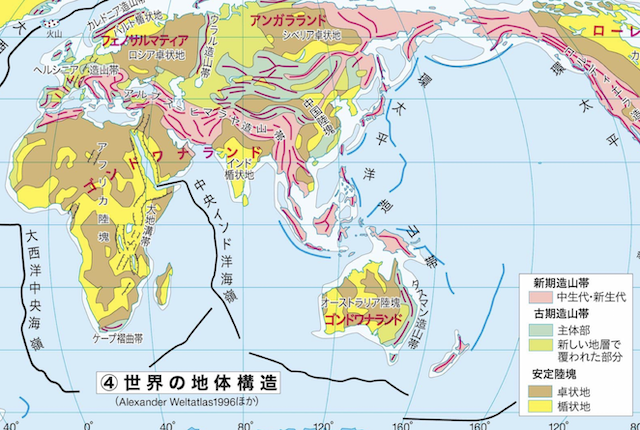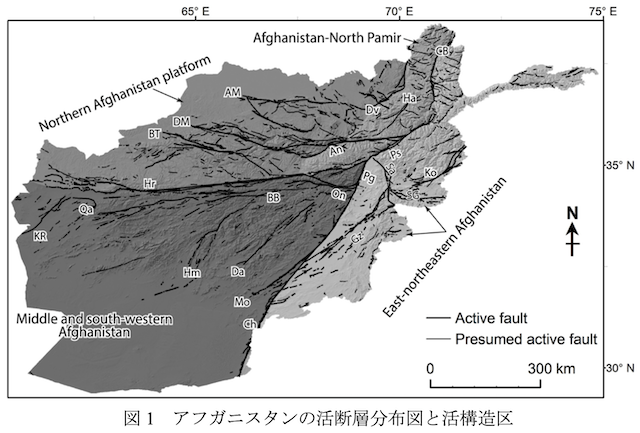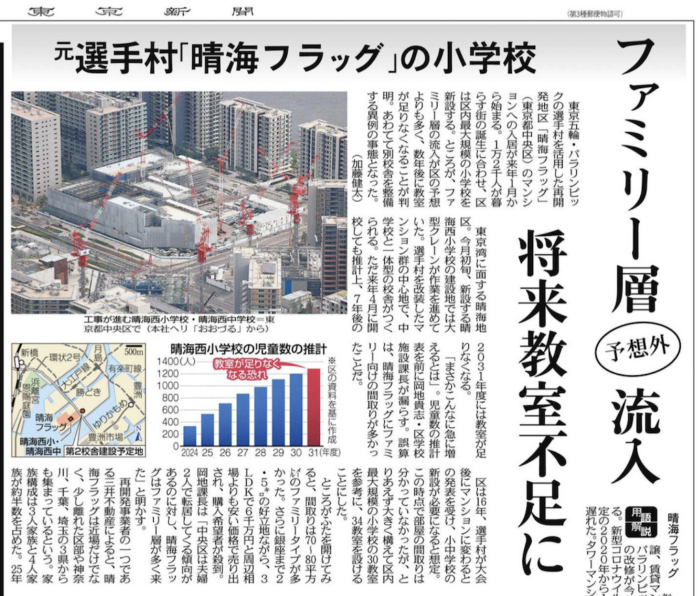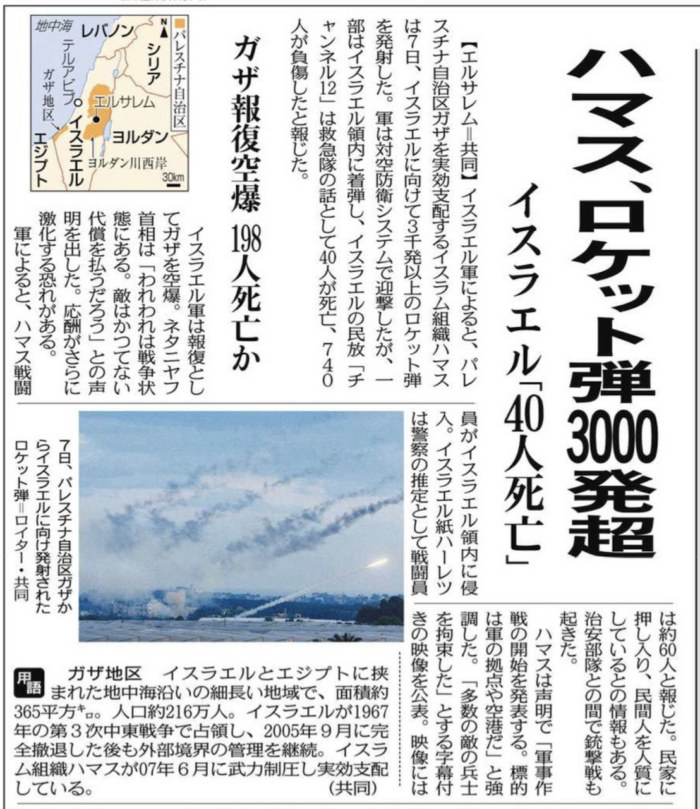本日の東京新聞朝刊に、タイのイスラム教徒がイスラエル大使館まで抗議デモを行ったとの記事が掲載されていた。タイの国民の95%は仏教である。そして、残りの5%がイスラム教で、その多くがマレーシアとの国境が近い南部に集まっている。世界史でいうと、14世紀から19世紀にかけて、ちょうどタイの南部にマレー系のパタニ王国というイスラム国があったことに由来する。
Wikipediaによると、旧パタニ領の一部の地域である深南部三県では、住民のタイ政府に対する反発と、黄金時代のパタニへのあこがれから、パタニ王国再興を大義名分にした分離独立運動の動きがあるとのこと。
今回の件に始まったことではないが、タイは地域的に中国の影響が強く、タイ南部の独立運動が周辺の大国の思惑に利用される懸念がある。